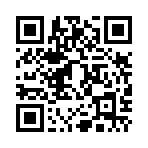扶養義務についての報道から、考えてみました
2012年11月13日
生活保護制度:厚労省の見直し案、特別部会の部会長が異論
毎日新聞 2012年11月12日
宮本太郎北海道大大学院教授は12日、国会内で開かれた民主党の会合で、生活保護制度の見直しに関する厚生労働省素案が受給申請者の親族に扶養できない理由の説明を義務づけていることについて「官僚制の管理機能強化が本当に必要か。効果があるのか」と述べ、異論を唱えた。宮本氏は見直し案を議論し、年内に成案をまとめる社会保障審議会(厚労相の諮問機関)特別部会の部会長を務めている。
宮本氏は、同省素案が生活保護受給者に健康管理の徹底を義務づけている点にも「生活への介入で、あえて書き込む必要があるのか」と疑問を示した。さらに財務省を、生活保護見直しを財政削減の観点から進めているとして批判した。生活保護を巡る管理強化については、受給者の支援団体も「申請をためらわせ、結果的に必要な人が受給できなくなる恐れがある」と懸念している。
【遠藤拓】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「扶養義務」の強要と思える生活保護の運用は、そもそも生活保護がその基本に「本人申請」を定めている事に反します。
人は、生活を含む自由な人格権を有していますが、本人申請の「精神」は、その人を尊重する所から来ています。「緊急保護」の条項が定められているのも、その為です。
ですから、扶養義務の「証明」という形で厳しく「強要」とも取れる制度運用がなされるとするならば、その逆の扶養義務者の保護を必要とする当人を差し置いての生活保護申請も受け付けるようにするのが筋となると思います。
これらの事が行われるとすれば、法の精神に反する、人格権の侵害がまかり通る事になります。
ましてや、保護申請者に保護が必要となるまで扶養義務を果たさなかった当事者と扶養義務者の『過去事情』に、「行政」が介入することが容認されるならば、個人情報保護の原則も崩される事になります。生活保護行政以外の所でも、行政の強権的な介入が認められる事に拡大していきます。警察の捜査にも、市民の権利を守る為に多くの制約・制限がある事は、自由な人格権守る為のものですが、その事で捜査に支障をきたしてもいますが、「警察国家」にしないと云う、そもそもは憲法の精神に基づくものです。
また、ある意味で瑣末な事ですが、「説明義務」に反した場合はどうするのか。反しているかいないかは誰が調査するのか。違反は、違法と行為として刑事罰の対象にするのか。行政の肥え太りだけを生み出し、予算の節約では無く増大が予想され、本末転倒でも良いとするならば、意図している本音は、支給額はへして、その数倍の管理運営予算を分捕り、役人を増やそうと云うものです。
現状でさえ、「扶養義務者」への連絡が重荷になって、生活保護申請を躊躇する方が沢山います。野宿に落ちる前に多大な迷惑をかけてきた事の負い目、既に諍いがあって縁が切れてしまっている場合など、過去を蒸し返されるよりは野宿を辛抱する方がましだと考えてしまうのです。野宿にまで成っていなくても、やはりこれ以上迷惑をかけられないと、保護を申請しない方も沢山おられます。
扶養義務を、これまで以上に厳しく問いただせば、更に保護申請がしにくくなります。
行政として、捕捉率20%という、「先進国」最低の現状を、憲法25条を護る仕事をしている立場から考えて、情けなくは無いのだろうか。
毎日新聞 2012年11月12日
宮本太郎北海道大大学院教授は12日、国会内で開かれた民主党の会合で、生活保護制度の見直しに関する厚生労働省素案が受給申請者の親族に扶養できない理由の説明を義務づけていることについて「官僚制の管理機能強化が本当に必要か。効果があるのか」と述べ、異論を唱えた。宮本氏は見直し案を議論し、年内に成案をまとめる社会保障審議会(厚労相の諮問機関)特別部会の部会長を務めている。
宮本氏は、同省素案が生活保護受給者に健康管理の徹底を義務づけている点にも「生活への介入で、あえて書き込む必要があるのか」と疑問を示した。さらに財務省を、生活保護見直しを財政削減の観点から進めているとして批判した。生活保護を巡る管理強化については、受給者の支援団体も「申請をためらわせ、結果的に必要な人が受給できなくなる恐れがある」と懸念している。
【遠藤拓】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「扶養義務」の強要と思える生活保護の運用は、そもそも生活保護がその基本に「本人申請」を定めている事に反します。
人は、生活を含む自由な人格権を有していますが、本人申請の「精神」は、その人を尊重する所から来ています。「緊急保護」の条項が定められているのも、その為です。
ですから、扶養義務の「証明」という形で厳しく「強要」とも取れる制度運用がなされるとするならば、その逆の扶養義務者の保護を必要とする当人を差し置いての生活保護申請も受け付けるようにするのが筋となると思います。
これらの事が行われるとすれば、法の精神に反する、人格権の侵害がまかり通る事になります。
ましてや、保護申請者に保護が必要となるまで扶養義務を果たさなかった当事者と扶養義務者の『過去事情』に、「行政」が介入することが容認されるならば、個人情報保護の原則も崩される事になります。生活保護行政以外の所でも、行政の強権的な介入が認められる事に拡大していきます。警察の捜査にも、市民の権利を守る為に多くの制約・制限がある事は、自由な人格権守る為のものですが、その事で捜査に支障をきたしてもいますが、「警察国家」にしないと云う、そもそもは憲法の精神に基づくものです。
また、ある意味で瑣末な事ですが、「説明義務」に反した場合はどうするのか。反しているかいないかは誰が調査するのか。違反は、違法と行為として刑事罰の対象にするのか。行政の肥え太りだけを生み出し、予算の節約では無く増大が予想され、本末転倒でも良いとするならば、意図している本音は、支給額はへして、その数倍の管理運営予算を分捕り、役人を増やそうと云うものです。
現状でさえ、「扶養義務者」への連絡が重荷になって、生活保護申請を躊躇する方が沢山います。野宿に落ちる前に多大な迷惑をかけてきた事の負い目、既に諍いがあって縁が切れてしまっている場合など、過去を蒸し返されるよりは野宿を辛抱する方がましだと考えてしまうのです。野宿にまで成っていなくても、やはりこれ以上迷惑をかけられないと、保護を申請しない方も沢山おられます。
扶養義務を、これまで以上に厳しく問いただせば、更に保護申請がしにくくなります。
行政として、捕捉率20%という、「先進国」最低の現状を、憲法25条を護る仕事をしている立場から考えて、情けなくは無いのだろうか。
Posted by 谷本 at 13:04│Comments(0)
│生活保護法の改定
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。