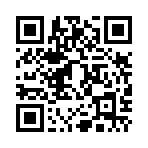制度を脅しに使うのかぁ~?
2011年11月29日
生活保護:職業訓練中断で停止も 厚労省方針、都や大阪市などと協議
毎日新聞 2011年11月26日 東京朝刊
厚生労働省は、求職者支援制度に基づく職業訓練を受ける生活保護受給者が理由なく訓練を中断した場合、生活保護を打ち切ることを検討する方針を固めた。同省は「本人が訓練を希望し、ハローワークも就労の可能性が高まると認めたのに合理的な理由なく欠席を続けた場合などを想定している」と説明するが、就労支援強化の名目で安易な打ち切りが乱発される懸念もある。
7月時点で生活保護受給者は205万人を突破し、過去最多を更新。保護費も今年度予算で3・4兆円に達している。厚労省は東京都や大阪市などと協議を続け、今回の方針は12月のとりまとめに盛り込まれる見通し。
求職者支援制度は失業者らが無料で職業訓練を受けられ、10月から法に基づく制度として恒久化された。低収入の場合は月10万円が支給され、生活保護との併用も可能だ。
厚労省保護課は「稼働能力があるのに保護に頼るのは望ましくない。しかし訓練を無理やり受けさせるという趣旨ではない」としており、訓練を中断した受給者が福祉事務所による指導でも改めない場合、保護の停止や廃止を検討するという。
このほか、改革案としては102億円(09年度)に上る保護費の不正受給対策として、告発を増やすための基準の策定も警察庁と協議のうえ検討する。また、保護費の半分を占める医療扶助を抑えるため、医療機関側の過剰診療を防ぐマニュアルの導入なども提案する。【石川隆宣】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
求職支援拒否なら保護費打ち切り 国と地方が見直し案
2011/11/26 02:02 【共同通信】
厚生労働省は25日、生活保護の受給者が「求職者支援制度」(10月開始)の職業訓練を受講できるのに拒否した場合、生活保護の打ち切りを可能とする方向で検討に入った。実務を担う地方自治体側も大筋で合意した。
生活保護の受給者は7月に過去最多の205万人超を記録。働ける現役世代の増加が目立ち、就労支援が急務となっている。求職者支援制度が整備されたことから、制度を活用できるのに、職業訓練を受けて仕事に就く意欲をみせない受給者には、厳しく対処する。年3兆円規模の保護費を抑制したい意向もあるとみられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二つの新聞記事で、最も大事なところに大きな違いがあるので、?です。
しかし、「求職者支援制度」の職業訓練が、共同通信の言う「職業訓練を受講できるのに拒否した場合」の打ち切りならば、仕事が決まらない限り、訓練校に通い続けなければならない事態もある様に思います。当事者の向き不向きに関わらず、ケース和カーからの指導がある事になります。不向きな物までは受講させないとすると、数に限りが出てきます。また、受講したからと云って、仕事につながるとは思えないことがあります。
現在のパソコン教室の様に、初心者以下の知識しか習得できない様な物もあります。
制度とそれを利用した保護打ち切りは、一時期のあだ花の様に思えます。
毎日新聞 2011年11月26日 東京朝刊
厚生労働省は、求職者支援制度に基づく職業訓練を受ける生活保護受給者が理由なく訓練を中断した場合、生活保護を打ち切ることを検討する方針を固めた。同省は「本人が訓練を希望し、ハローワークも就労の可能性が高まると認めたのに合理的な理由なく欠席を続けた場合などを想定している」と説明するが、就労支援強化の名目で安易な打ち切りが乱発される懸念もある。
7月時点で生活保護受給者は205万人を突破し、過去最多を更新。保護費も今年度予算で3・4兆円に達している。厚労省は東京都や大阪市などと協議を続け、今回の方針は12月のとりまとめに盛り込まれる見通し。
求職者支援制度は失業者らが無料で職業訓練を受けられ、10月から法に基づく制度として恒久化された。低収入の場合は月10万円が支給され、生活保護との併用も可能だ。
厚労省保護課は「稼働能力があるのに保護に頼るのは望ましくない。しかし訓練を無理やり受けさせるという趣旨ではない」としており、訓練を中断した受給者が福祉事務所による指導でも改めない場合、保護の停止や廃止を検討するという。
このほか、改革案としては102億円(09年度)に上る保護費の不正受給対策として、告発を増やすための基準の策定も警察庁と協議のうえ検討する。また、保護費の半分を占める医療扶助を抑えるため、医療機関側の過剰診療を防ぐマニュアルの導入なども提案する。【石川隆宣】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
求職支援拒否なら保護費打ち切り 国と地方が見直し案
2011/11/26 02:02 【共同通信】
厚生労働省は25日、生活保護の受給者が「求職者支援制度」(10月開始)の職業訓練を受講できるのに拒否した場合、生活保護の打ち切りを可能とする方向で検討に入った。実務を担う地方自治体側も大筋で合意した。
生活保護の受給者は7月に過去最多の205万人超を記録。働ける現役世代の増加が目立ち、就労支援が急務となっている。求職者支援制度が整備されたことから、制度を活用できるのに、職業訓練を受けて仕事に就く意欲をみせない受給者には、厳しく対処する。年3兆円規模の保護費を抑制したい意向もあるとみられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二つの新聞記事で、最も大事なところに大きな違いがあるので、?です。
しかし、「求職者支援制度」の職業訓練が、共同通信の言う「職業訓練を受講できるのに拒否した場合」の打ち切りならば、仕事が決まらない限り、訓練校に通い続けなければならない事態もある様に思います。当事者の向き不向きに関わらず、ケース和カーからの指導がある事になります。不向きな物までは受講させないとすると、数に限りが出てきます。また、受講したからと云って、仕事につながるとは思えないことがあります。
現在のパソコン教室の様に、初心者以下の知識しか習得できない様な物もあります。
制度とそれを利用した保護打ち切りは、一時期のあだ花の様に思えます。
正論も、無きがごとしです
2011年11月24日
生活保護 最多だが低利用率
<東京新聞>2011年11月24日
生活保護の受給者数は、今年七月現在で二百五万四百九十五人(速報値)を超え、一九五〇年に現行の生活保護制度が始まって以来、過去最多を更新した。高齢の受給者の増加や、働ける世代の受給が伸びていることが主な背景だが、他の先進国と比べると利用率は低い。「必要な人がまだ利用できていない」と訴える声も上がる。 (稲田雅文)
「心にゆとりができ、前向きな気持ちになりました」。愛知県の四十代男性は、四歳の長男を育てる父子家庭。九月に生活保護を申請した。
以前、ハローワークに通ったが、なかなか仕事が見つからない。面接で父子家庭だと伝えると断られることも多かった。
ようやく見つけた今の運送の仕事で稼げるのは、月八万~十二万円程度。ここから家賃や保育料、光熱費などを払うと、わずかしか残らなかった。
生活保護を受けられたのは、法律家の助言があったから。弁護士らでつくる「東海生活保護利用支援ネットワーク」に参加する司法書士に相談すると、「生活できる収入ではない」と受給を勧められた。抵抗感はあったが、働きながらでも不足した収入を補ってもらえ、家賃や保育料の負担がなくなることなどを説明されて納得した。
保護費と賃金と合わせて収入が約十五万円と安定。「冬も安心して越せる」と気持ちが落ち着いた。少しでも収入を得ようと、空いている時間にできる仕事を増やした。
同ネットワーク事務局長の森弘典弁護士は「低年金の高齢者など、実際は生活保護が申請できる水準の収入の人は多い。しかし、生活に困って窓口に行っても、まず一回目では申請は受け付けないことが多い」と語る。
自治体の窓口では「働けるのではないか」「頼れる親類がいるのでは」などと聞かれ、うまく状況を説明できずに申請をあきらめる人も多い。ところが、同じ人が同ネットワークの法律家とともに窓口に行くと、すんなりと申請できるという。
◇
「利用者の増加ではなく、貧困の拡大が問題だ」-。「生活保護問題対策全国会議」は九日、生活保護受給者が最多となったことを受けて東京都内で会見し、必要な人がまだ生活保護を受けられていないなどとする見解を発表した。
同会議の小久保哲郎弁護士は「保護受給者数の人口比である保護率で比べれば、過去最多だった一九五一年当時の三分の二程度。実質的に最多とは言えない」と語った。
現在の日本の保護率は1・6%。小久保弁護士によると、他の先進国の保護率はドイツ9・7%、イギリス9・3%、フランス5・7%と、日本よりも数倍高い。全国民の中で生活に苦しむ人の割合を示す「相対的貧困率」は二〇〇九年時点で16・0%で、生活保護制度は十分の一しかカバーしていない。
日弁連も同日、「生活保護のより一層の活用を求める会長声明」を出した。受給者の増加は▽長引く不況と非正規雇用の増加で、ワーキングプアが増えている▽失業時の所得保障制度が弱い▽最低生活保障としての年金制度が確立していない-ことが背景で、貧困を一手に生活保護制度が支えていると指摘。「低賃金の不安定雇用をなくし、社会保障制度を拡充して対応すべきだ」とする。
<生活保護受給世帯の内訳> 生活保護を受けているのは148万世帯。65歳以上の高齢者世帯が63万527世帯と全体の42.6%を占め、傷病者世帯(21.6%)、障害者世帯(11.3%)、母子世帯(7.6%)と続く。
近年、増えているのが、働ける年代なのに失業などで受給する人を含む「その他の世帯」で、25万1176世帯と全体の17.0%。2008年のリーマン・ショック前の2倍で、背景には雇用が不安定な非正規労働者の増加がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
派遣業法改正の骨抜きや、生活保護の改悪は、許しがたいです。
貧困が生み出される世の中の仕組みが変わらないならば、生活保護申請の窓口で、支援者が頑張らなければと思っています。
<東京新聞>2011年11月24日
生活保護の受給者数は、今年七月現在で二百五万四百九十五人(速報値)を超え、一九五〇年に現行の生活保護制度が始まって以来、過去最多を更新した。高齢の受給者の増加や、働ける世代の受給が伸びていることが主な背景だが、他の先進国と比べると利用率は低い。「必要な人がまだ利用できていない」と訴える声も上がる。 (稲田雅文)
「心にゆとりができ、前向きな気持ちになりました」。愛知県の四十代男性は、四歳の長男を育てる父子家庭。九月に生活保護を申請した。
以前、ハローワークに通ったが、なかなか仕事が見つからない。面接で父子家庭だと伝えると断られることも多かった。
ようやく見つけた今の運送の仕事で稼げるのは、月八万~十二万円程度。ここから家賃や保育料、光熱費などを払うと、わずかしか残らなかった。
生活保護を受けられたのは、法律家の助言があったから。弁護士らでつくる「東海生活保護利用支援ネットワーク」に参加する司法書士に相談すると、「生活できる収入ではない」と受給を勧められた。抵抗感はあったが、働きながらでも不足した収入を補ってもらえ、家賃や保育料の負担がなくなることなどを説明されて納得した。
保護費と賃金と合わせて収入が約十五万円と安定。「冬も安心して越せる」と気持ちが落ち着いた。少しでも収入を得ようと、空いている時間にできる仕事を増やした。
同ネットワーク事務局長の森弘典弁護士は「低年金の高齢者など、実際は生活保護が申請できる水準の収入の人は多い。しかし、生活に困って窓口に行っても、まず一回目では申請は受け付けないことが多い」と語る。
自治体の窓口では「働けるのではないか」「頼れる親類がいるのでは」などと聞かれ、うまく状況を説明できずに申請をあきらめる人も多い。ところが、同じ人が同ネットワークの法律家とともに窓口に行くと、すんなりと申請できるという。
◇
「利用者の増加ではなく、貧困の拡大が問題だ」-。「生活保護問題対策全国会議」は九日、生活保護受給者が最多となったことを受けて東京都内で会見し、必要な人がまだ生活保護を受けられていないなどとする見解を発表した。
同会議の小久保哲郎弁護士は「保護受給者数の人口比である保護率で比べれば、過去最多だった一九五一年当時の三分の二程度。実質的に最多とは言えない」と語った。
現在の日本の保護率は1・6%。小久保弁護士によると、他の先進国の保護率はドイツ9・7%、イギリス9・3%、フランス5・7%と、日本よりも数倍高い。全国民の中で生活に苦しむ人の割合を示す「相対的貧困率」は二〇〇九年時点で16・0%で、生活保護制度は十分の一しかカバーしていない。
日弁連も同日、「生活保護のより一層の活用を求める会長声明」を出した。受給者の増加は▽長引く不況と非正規雇用の増加で、ワーキングプアが増えている▽失業時の所得保障制度が弱い▽最低生活保障としての年金制度が確立していない-ことが背景で、貧困を一手に生活保護制度が支えていると指摘。「低賃金の不安定雇用をなくし、社会保障制度を拡充して対応すべきだ」とする。
<生活保護受給世帯の内訳> 生活保護を受けているのは148万世帯。65歳以上の高齢者世帯が63万527世帯と全体の42.6%を占め、傷病者世帯(21.6%)、障害者世帯(11.3%)、母子世帯(7.6%)と続く。
近年、増えているのが、働ける年代なのに失業などで受給する人を含む「その他の世帯」で、25万1176世帯と全体の17.0%。2008年のリーマン・ショック前の2倍で、背景には雇用が不安定な非正規労働者の増加がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
派遣業法改正の骨抜きや、生活保護の改悪は、許しがたいです。
貧困が生み出される世の中の仕組みが変わらないならば、生活保護申請の窓口で、支援者が頑張らなければと思っています。
生活保護が減らない原因はこれだ
2011年11月22日
製造業派遣「原則禁止」削除…民自公が大筋合意
政府提出の労働者派遣法改正案に盛り込まれた「製造業派遣」と「登録型派遣」をそれぞれ原則禁止する規定について、民主、自民、公明3党が両規定の削除で大筋合意したことが15日、分かった。両規定に反対する自公両党に民主党が譲歩した。
同改正案は修正のうえ、今国会で成立する見通しとなった。
同改正案は派遣労働者の待遇改善を目指し、2010年の通常国会に提出された。改正案には、〈1〉派遣元企業が得る手数料の割合を明示するよう義務づけ〈2〉製造業への派遣は原則禁止〈3〉仕事がある時だけ派遣元と雇用契約を結ぶ登録型派遣は秘書や通訳などの専門26業種以外で原則禁止――などを規定した。
このうち、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止には、経済界に「急な仕事の発注に対応できない中小企業が影響を受ける」などと反対意見が強い。自公両党も経済界の懸念を踏まえて政府案を批判。同改正案は衆院で継続審議となり、今国会でも実質的な審議に入れないままになっている。
このため、民主党は、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止以外の待遇改善策の実現を急ぐ必要があると判断し、両規定の削除に応じることにした。
(2011年11月15日11時15分 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業利益のための法律は、失業即生活保護やホームレスの現状を作っています。
政治が貧困の現状に頓着せず、企業の代弁者として法律をいじる事は、許せません。
政府提出の労働者派遣法改正案に盛り込まれた「製造業派遣」と「登録型派遣」をそれぞれ原則禁止する規定について、民主、自民、公明3党が両規定の削除で大筋合意したことが15日、分かった。両規定に反対する自公両党に民主党が譲歩した。
同改正案は修正のうえ、今国会で成立する見通しとなった。
同改正案は派遣労働者の待遇改善を目指し、2010年の通常国会に提出された。改正案には、〈1〉派遣元企業が得る手数料の割合を明示するよう義務づけ〈2〉製造業への派遣は原則禁止〈3〉仕事がある時だけ派遣元と雇用契約を結ぶ登録型派遣は秘書や通訳などの専門26業種以外で原則禁止――などを規定した。
このうち、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止には、経済界に「急な仕事の発注に対応できない中小企業が影響を受ける」などと反対意見が強い。自公両党も経済界の懸念を踏まえて政府案を批判。同改正案は衆院で継続審議となり、今国会でも実質的な審議に入れないままになっている。
このため、民主党は、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止以外の待遇改善策の実現を急ぐ必要があると判断し、両規定の削除に応じることにした。
(2011年11月15日11時15分 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業利益のための法律は、失業即生活保護やホームレスの現状を作っています。
政治が貧困の現状に頓着せず、企業の代弁者として法律をいじる事は、許せません。